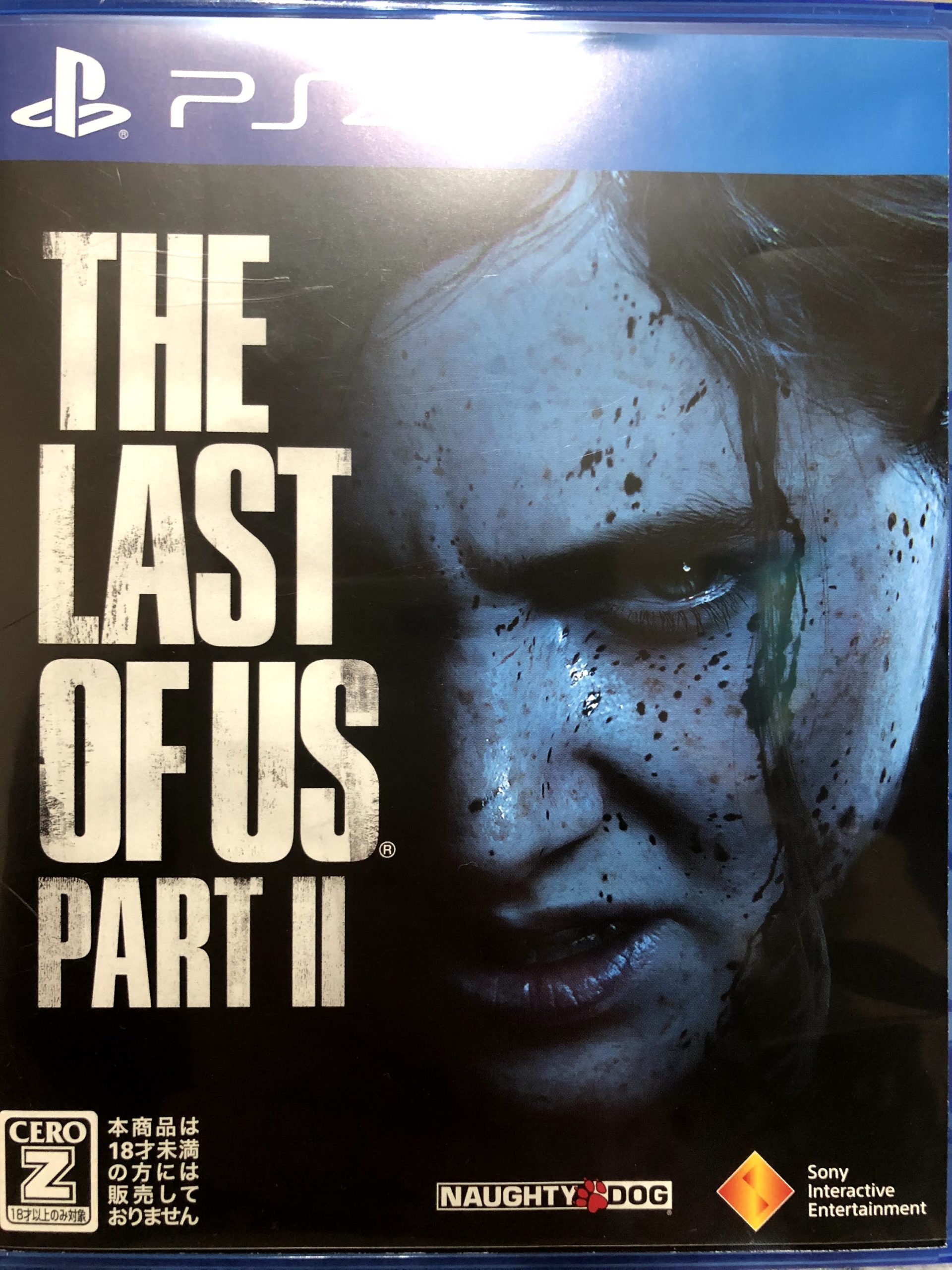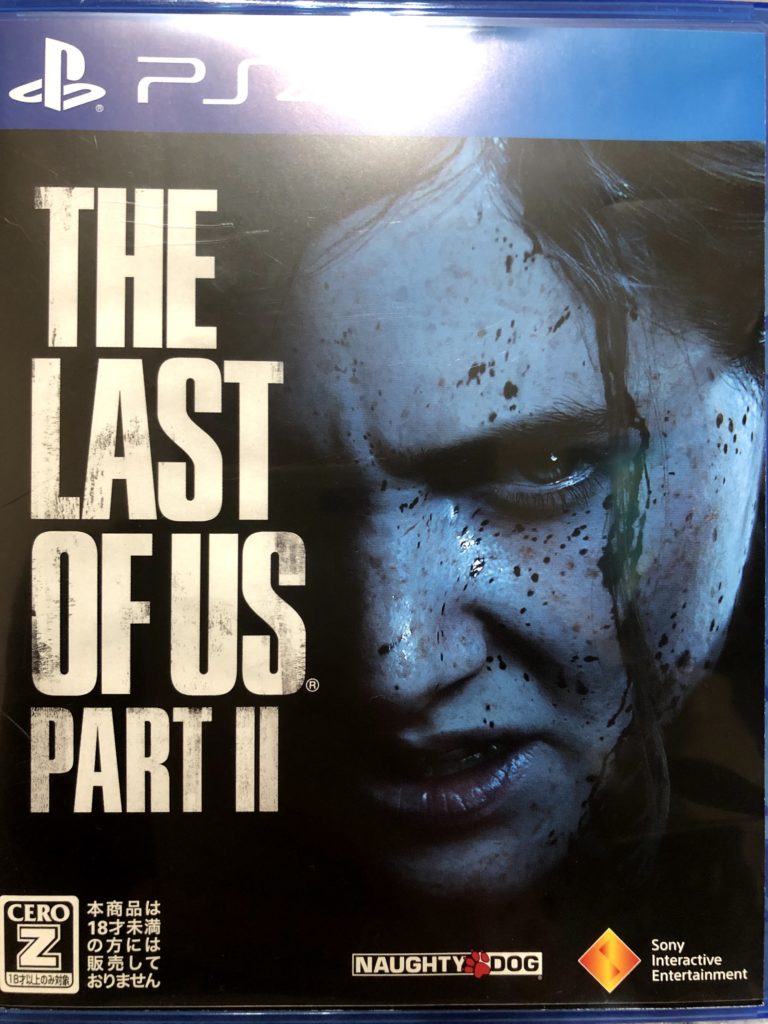
Sony Interactive EntertainmentのPlayStation4専用タイトル、The last of Us Part IIをクリアしました。発売したのが6月19日なので、4ヶ月かかっていますが、間にGhost of Tsushimaをプレイしていたりしたので…
Ghost of Tsushimaはトロフィーコンプリートしましたが、The Last of Us Part IIはトロフィーは30%程度ですね。トロフィーからも分かるように、満足度はGhost of Tsushimaの方が高いです。
何故にプレイしたのか?
Naughty Dogのタイトルは、ゲーム開発者の間では評判が良いんです。描画やコンテンツの作りこみのクォリティが高い、という意味です。
ですので、皆がプレイして、どれくらいのクォリティの作品を出してきているのか?と、ベンチマーク的な扱いを受ける訳です。
描画だとSIGGRAPHに今年もいくつか講演が出ていますね。こういう発表の内容を見て、他のゲーム会社が同じように実装していく訳です。
描画以外では、The Last of Us Part IIと言えば、Motion Matchingという言葉が良く聞きます。これは、プロシージャルアニメーションの一環で、アニメーションが滑らかに見えるようにする為の技術です。
Ubisoftが2016年にGDCで発表し、For Honorに使われた技術です。
CAPCOMでも取り入れていて、講演資料が出ていますね。
簡単に言うと、長いアニメーションを細分化したデータを持っておいて、アニメーションが遷移する時に、次のアニメーションとして一番良さそうなデータを選んで再生するという技術ですね。
Play Station 4世代からはメモリが多くなったので、長いアニメーションデータをメモリに持って置けるようになったから出てきた技術ですね。
何にでも使えるという訳ではなくて、用途を限って使っていたみたいですね。ランタイムで計算してアニメーションの遷移を決めるので、コントールしづらいだろうな。というイメージですね。カットシーンからゲームへの繋ぎなどは、アニメーターの頑張りが大きいかと思います。
プロシージャルアニメーションと言えば、ロープの動きが凄い良いと話題になりましたね。
この様に、素晴らしいクォリティの仕上がりとなっているので、実際にプレイして、これらの技術がどの程度ゲームの面白さに貢献しているのかを調べたくなるものです。
長いストーリーと、苛烈な残虐表現
一作品目も長かったけれど、今回も、とにかく長い。長く感じる原因は、基本的に話の内容が暗くて重いのと、プレイへ求められる緊張感の高さだと思われます。
ストーリーに関しても1作品目は男性主人公だったのが、2作品目は主人公が女性に代わっている事、その女性主人公がレズという事が、炎上した理由みたいですね。
私はそういうところには余り興味がないので、あ、そうなんだ。レズなのか。最近はLGBTの人を尊重する社会だしね。という感じで余り気にしていませんでした。そんな事よりも、ストーリーが重すぎて、そっちの方が気が滅入りましたね。
1作品目は、生き抜くんだ!という強い意志を持って大陸を横断する、そして奇病を治療するというのが目的でした。生きる為の目的ですね。
2作品目では、完全に復讐の鬼と化してターゲットを探し出して追い詰めて殺すのが目的です。
生きるという目的から、殺すという目的に代わっているのが大きな変化です。
ディレクターが狙ってこう作ったんだと思うんですが、とにかくギャップが凄いですね。敵を討ちたい気持ちも分かるし、実際にターゲットを殺していく中で、エリーが様々な葛藤を抱えている事が表現されています。
人物の感情を表現する。という意味では、このゲームは最高レベルだと思います。
緊張感のあるバトルと凄惨な残虐表現
バトルもなかなかの疲労感がありました。敵と遭遇して、油断すれば簡単に死ぬし、倒す時の残虐表現がかなりエスカレートしていて、酷い殺し方をするので、プレイしていて精神的な疲労が大きいです。
今回の残虐表現は凄かったですね。こういうゲームを開発しろと言われて毎日こういうシーンを何度もプレイしたら鬱になりそうですね…それくらい凄かったです。
残虐表現じゃないですけれど、ゲームにゴキブリを出す事になって、アーティストがゴキブリの資料をSlackにぺたぺた貼っていた事はありましたね。ああいうのが平気な人は本当に凄いです。
God of Warもなかなかな残虐表現でしたが、神話を表現しているので、スケールが大きすぎて現実離れしている分、残虐性も若干は薄まります。The Last of Us Part IIは、リアルな人間同士の殺し合いなのでグロテスクな部分が目立ちますね。
それ以外で気になったのは、謎の病気の感染爆発によって人口が減っているはずなのに、その貴重な生き残りの人間を何の躊躇もなく殺していく事でした。え?こんなに殺して回っていたら、人類は滅亡するのでは?と、気になって仕方がなかったですね…
丁寧な作りこみ
演出部分は本当に丁寧に作りこまれていましたね。
カットシーンを見ていて、その世界に引き込まれていくような印象を受けました。なので、ゲームプレイに戻る時に、あ、ここからはプレイするのか。と、ちょっと意識して気持ちを切り替える必要がありましたね。
ゲームとカットシーンの繋ぎが本当に丁寧に作りこまれているのと、数が本当に多かったのです。これは根気のいる作業を頑張っているんだと思いました。
例えば、ゲームプレイパート(プレイヤーが操作している)と、カットシーンパート(自動的にプレイヤーが動いている演出)がスムーズに繋がっていますが、それぞれの出入りの時に、プレイヤーの状態をスムーズに繋いでいるかと思います。
この動画が凄く分かりやすいですが、作業台に入る時に流れ、襲われてからゲームプレイに復帰する時、更には敵を全滅させた後に、作業台で銃をカスタマイズする時の流れが凄くスムーズですよね。
こういう部分の作りこみを省略しているタイトルだと、暗転させから武器を切り替えて終わりですよね。動画を細かく見ると分かりますが、カスタマイズ内容を決定した瞬間に銃の影がちょっとだけちらつきます。この時にカスタマイズ後の銃に切り替えているんだと思います。パーツの入れ替えが分からないように、エリーの体でカスタマイズ部分を隠していますよね。
そういう細かい作りこみ1つ1つがゲームの臨場感を最高の物に仕上げていますよね。
世知辛い話ですが、ゲーム開発は開発コストと売り上げから利益を得るビジネスなので、どれだけ作りこめるかはその企業の体力と、タイトルが持っている販売力次第です。The Last of Usは一作品目が売れている事と、Sonyの子会社のSony Interactive Entertaiment、更にその子会社のNaughty Dogのタイトルという事で、開発予算が大きいのだと思います。
まとめ
プレイして後悔するようなタイトルではないですが、とにかく話が重くて、残虐なので、覚悟してプレイしましょう。
技術的な良さがどうとかよりも、プレイして面白いかどうかが全てだと思っていますが、技術レベル高いと羨ましくなりますね。
次回作も期待して待っています!